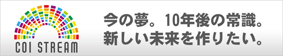NU COIマガジン 第1回「ゆっくり自動運転®が拓く未来」
2018/07/25
〔目 次〕
自分で車を運転できない人にとって、公共交通は頼みの綱だ。愛知県の中山間地域に住むAさんにとっては、コミュニティバスがこれにあたる。しかし、ひとつ悩みがあった。最寄りのバス停が坂の下にあるのだ。
最近膝が痛いAさんにとって、坂道の上り下りがつらい。しかし、バスに乗らなければ、買い物にも、病院にも、地域交流サロンにも行くことができない。どれも元気に生活するためには不可欠なこと。バス停まで行くことは膝のことを考えると気が進まないが、行かなければ満足な生活ができない。

そんなAさんみたいな人は、全国にはたくさんいるだろう。
町村規模の地域に居住する人の内、約5割もの人が、徒歩圏内にコンビニエンスストアあるいはスーパーなどの小売店がないという※1。そのような地域では、自家用車を利用する人が多いが、Aさんのように運転できない人は、誰かの運転に頼るか、多少不便でも公共交通機関に頼らざるを得ない。不便さを抱えて、生活しているといえる。
※1 内閣府「高齢者の経済・生活環境に関する調査」(平成28年)
しかし、そんな不便さも、「ゆっくり自動運転®」があれば解消される、と名古屋大学COIの研究リーダーである森川教授は語る。
「たとえば、自動運転の超小型モビリティが呼べば玄関先まで迎えに来て、バス停まで送ってもらえる。帰りもバス停からそのモビリティで帰れる。また、自動運転なので、送り届けた後は自分で駐車スペースまで戻る。バス停まで移動する負担も、運転する負担もない。それを叶えるシステムがゆっくり自動運転®です」
「ゆっくり自動運転®」とは、名古屋大学COIが研究開発している「低速度・地域限定のドライバーレスな移動サービス」のこと。名古屋大学COIでは、研究リーダーの森川教授やチームリーダーの竹内准教授の下、研究者、企業研究者・技術者などの総勢20名を超えるメンバが一丸となって、これの研究開発に取り組んでいる。
 |
| ゆっくり自動運転チーム |
先の例では超小型モビリティだったが、バスといった大型車両への搭載も可能だ。その想定される活用範囲は幅広く、ラストマイル交通や近距離移動サービス用バス、自動バレーパーキング、カーシェアリング回送など、多岐に渡る。
大きな特徴のひとつが、時速20km以下、という車としてはゆっくりな速度だ。
どうして“ゆっくり”なのか。
その意義として森川教授は、技術的社会的障壁の低下を挙げる。時速40~60kmといった“ふつうの速度”よりもゆっくりな自動運転とすることで、安全性を高めることができ、人と社会との協調も可能となる。加えて、地域や経路を限定にすることで特区などでの対応もいち早く可能になるという。
また、ゆっくりで、地域・経路限定であっても、ドライバーレスの移動サービスを実装し、一般の方でも利用できるようにすることで、未来の社会を実感できることの効果も大きい。
「これまでになかった価値を生み出すこともできると思います。たとえば、ゆっくりだから、“走行中”に“乗っている人”と“歩行者”とのコミュニケーションが可能になります。これはふつうの速度の自動運転ではむずかしい。もしかしたら、移動に対する人々の価値観も大きく変わるかもしれません」と森川教授は未来の社会を見据える。
「速度や地域等を限定して技術的障壁を下げることで、早期にテストコース外の様々な場所での実証実験が可能になります。これには大きなメリットが2つもあります」とチームリーダーを務める竹内准教授は語る。
まずひとつが、完全自動運転の実用化(社会実装)が早くなること。シミュレーションやテストコースではわからない課題が明確になり、それを解決できるシステムに改善することで、次の段階に進むことができる。これを繰り返すことで、早期の実用化が可能になるという。そして、その早さが、もう一つのメリットをもたらす。
完全自動運転が当たり前にある社会の構築への貢献である。
「人や社会が完全自動運転技術を受け入れるには、技術が完成するだけではむずかしいと我々は考えています。」
石橋を叩いて渡る、という言葉があるように、技術的には安全だとわかっていても、人がすぐに安心して使いだすとは限らない。これまでにない新しい技術に対しては、その傾向は強くなるだろう。
検討すべきことは山積みだ。
自動運転車があることが人や地域コミュニティにとってどういう意味を持つのか。自動運転車をどういう仕組みで運用するとよいのか。自動運転車が社会に存在するためにはどのような制度や環境、交通インフラが必要なのか。
シミュレーションでわかることには限界がある。中には、実際に走らせてはじめて見える課題もあるだろう。だからこそ、早くにテストコースの外で自動運転車を走らせることが重要なのだと、竹内准教授は話す。
「まずは公道実験で、ゆくゆくは実用化したゆっくり自動運転®を搭載した車が町中を走ることで、開発・実証される技術や蓄積されるノウハウ、そして、そこから生まれる新しい価値によって、より高速なレベル4やレベル5の自動運転の研究とその実用化は加速されることになると思います」
「実用化のためには、安全に着実に実験を繰り返すことが必要。そのため、超小型EV(コムス)を実験車両として採用し、自動走行に必要な機能のすべてを搭載しました」と奥田助教は説明する。
レーザーセンサ(LiDAR)で周辺環境を認識し、3次元地図データを踏まえて今自分がどこにいるかを推定する。次に、対向車や歩行者の挙動を先読みし、軌道生成技術で最適な走行経路を決める。それを繰り返すことで自動走行が可能になるのだ。
加えて、ゆっくり自動運転®では、人や社会との協調も目指しており、それを可能にするのが自動運転知能とインフォディスプレイだ。
自動運転知能が、周辺環境も踏まえて「今どう動くべきか」に加えて、周囲の歩行者や他車に伝えるべき情報も判断し、車両上部に設置したインフォディスプレイにその情報を表示する。そうすることで、自動運転車が異物にならず、周辺環境と調和した状態を目指すのだ。

「安全に実験を繰り返すことが第一。人間による操作が最優先になるシステムを組み、安定して作動する信頼性が高いコントローラーを採用して、操舵や速度制御、停止といった下位の制御ができるようにしました。だからこそ、上位の複雑な制御にも挑戦できます」
はじめての公開実証実験は、平成29年11月27日に、愛知県豊田市の足助地区にて行われた。コミュニティバスのバス停から近所のお寺までの約600mの距離を自動走行した。利用者役のスタッフが乗車したが、もちろんハンドルやブレーキなどは操作していない。
当日は、近隣住民や小学生が見学に来ており、走行中にスタッフが手を振ると歓声が上がった。研究者への質問タイムでは様々な質問が飛び交った。テストコースの外での実験だからこその光景である。
今度は、オンデマンド型の地域内交通を想定した実験を、愛知県春日井市で行う予定だ。
ゆっくり自動運転®は、ゆっくりとだが着実に、未来への道を歩んでいる。この歩みは、完全自動運転が当たり前にある社会の実現の加速にもつながっていくだろう。
 |
 |
| 当日の様子(左:自動走行デモ、右:研究者への質問タイム) | |
※愛知県春日井市での公開実験について(プレスリリース)
./wp-content/uploads/2018/02/20180223pressrelease_koukaijikken.pdf
森川教授によれば、世界的に低速度の交通手段(slow transportation)の意義が見直されているという。
「人や社会と協調し、環境にも優しい移動手段。ゆっくり自動運転はこれを最新の自動運転技術で実現するもの。もちろん幹線道路などを走行する場合には、周囲と協調するためにより速い速度で走行する技術も併せ持つ必要も出てくるでしょう。社会的ニーズを見極めながら、いち早い社会実装を目指して研究開発を進めていきたい」
内閣府の調査によれば、高齢になっても現在住んでいる地域に住み続けたいと希望する人は年代問わず7割前後おり、特に高齢なほどその割合が高くなる※2。そのため、日々の生活を維持するためにも健康のためにも、買い物や通院のための外出手段の確保は重要となる。
自動車が外出手段に占める割合は大きく、特に地方都市圏においては約7割となる※3。自動車を保有している、あるいは免許を取得している場合、そうでない場合と比べて、1日当たりの移動回数が多いこともわかっている。車や免許がない人は、それだけ何らかの活動を行う機会を失っているともいえる。
※2内閣府「国土形成計画の推進に関する世論調査」(平成27年)
※3国土交通省「全国都市交通特性調査」(平成27年)
ゆっくり自動運転による様々なモビリティサービスが、そのような外出に対して不便を感じている人たちの手助けになることを、我々は目指している。
NU COIリサーチ「ゆっくり自動運転のチャレンジVol.1」
NU COIリサーチ「ゆっくり自動運転のチャレンジVol.2」
※「ゆっくり自動運転」は国立大学法人名古屋大学の登録商標です。
公開:2018/02/27
更新:2018/07/25