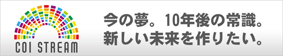NU COIマガジン第4回「名古屋大学COI若手顕彰受賞者インタビュー(1)」
2020/01/14
名古屋大学COIでは、若手参画メンバーの社会実装に向けての取組み、および将来に向けた新規性のある計画を対象とした顕彰制度「名古屋大学COI若手顕彰」を、2018年度から設けております。
その記念すべき第1回では、次の方々が受賞されました。〔受賞の様子(記事に移動)〕
産学官イノベーション賞 小野島 大介特任准教授(名古屋大学 未来社会創造機構)
プロジェクトリーダー賞 金森 亮特任准教授(名古屋大学 未来社会創造機構)
研究リーダー賞 赤井 直紀特任助教(名古屋大学 未来社会創造機構)
小野島さんは医療工学の、金森さんは土木工学交通系の、赤井さんは情報学の研究をそれぞれしています。
まったく異なる分野で活躍する3名に、受賞の感想や日頃の活動、研究への想いについてのインタビューを全3回にわたってお届けします。
――受賞、おめでとうございます。まずは受賞された内容とその感想を教えてください。
小野島 ラボ・オン・ドローンは、空気中の有害な微粒子など、バイオエアロゾルという生物的な成分を含むものを効率よくサンプリングしてくるデバイスで、バイオデバイス加工グループのテーマのスピンオフです。
受賞したことは非常に感謝しています。うまくいけばこのテーマをさらに大きく広げられます。受賞が大きな後押しになったと思っています。
赤井 自己位置推定という技術の研究です。これは読んで字のごとく、自分の位置を推定するという、一見大したことなさそうですが、実は自動運転の中では核となる技術です。推定というのは、もっともらしいものを予測することです。つまり、推定した結果が正しいかどうかという保証はどこにもありません。この推定結果の正しさを保証するためにはどうすればいいか、また失敗した時にどのように安全サイドに振るか、そしてどのように安全な自動運転システムをつくりあげるか、という研究を行っています。
受賞できたことは率直にうれしいです。また、地味な自己位置推定研究の必要性が、周りの人からも認めてもらえたという印象を受け、とても励みになりました。
金森 COIの枠組みではないところで、静岡市でMobility as a service(MaaS)の社会実装に向けた活動をしています。静岡鉄道グループでは、鉄道もバスもタクシーも商業施設もすべてポイントで連携しています。いわゆる情報銀行みたいなものも見据えながら、民間の目線と行政の目線の両方からデータ分析ができるとおもしろいかなと思っています。
受賞は良かったなと思います。なかなか研究論文に書けないような調整事項が多いですが、大学としてフィールドを持つことはいいと思い、活動しています。現状は人の動きは観測さえもできていないんですね。MaaSのアプリケーションは、どこに行ったかとか経由したかとか観測できるシステムですので、人の動きがようやく詳細に観測できはじめたところです。これから心理など行動の裏も含めてデータ分析をして研究していきたいと考えています。
――それでは、今の話とかぶる方もいらっしゃいますが、次は主にどんなことに取組んでいるか、COIに限らず教えてください。
金森 いわゆるMaaSは、日本では主に民間主導で実証実験が行われていますが、もう少し行政のウェイトを高めようと静岡市での取り組みでは考えています。その理由として、データの使い方が今後厳しくなってきて、民間利用だとGAFAみたいにけっこう不安が出てくるようなところもある。そこで実際に便益を享受できたり、間接的に地元に貢献できますよとか、税金みたいな感じでデータを提供するスキームを構築できればと考えています。自分のデータを提供することによって地域がよくなるっていうループが回るようになればいい。それによって、より継続的な社会実装ができるんじゃないかなと考えているところです。
赤井 僕が目的としていることは既存システムの限界を突破することです。自動運転がすごく流行ってますが、既存システムの限界を正しく把握している人は少ないように思えます。なので、過度に自動運転に対する期待だけが先行しているように感じます。そういう意味では、自動運転が未だに難しい技術であることを正しく広げていくのもひとつだと思います。また、既存システムの限界を突破するためにどういう方法が必要なのか、といったことも発信できればと思っています。
小野島 分離と分析化学を応用した健康と環境計測の技術開発を進めています。血中のがん細胞や水中の微生物を捕えてくる微細構造や、微量成分の検出に有効な機械学習のプログラムを研究したり、サンプルを取ってくるデバイスを機械化するようなIOTの研究なども進めています。
要素技術を中心に開発していると、装置を開発するリソースが足りなくなる時があります。ですので、それぞれの要素を組み合わせたときに本当に成り立つのか、プロトタイピングを早めにしてあたりをつけて、社会実装までのロードマップを引くアプローチをCOIでは取っています。もちろん、技術開発に特化している場合と比べて、開発条件が制限されることもありますが、その分、ある程度利用可能なものの組み合わせで新しいものを生み出すイノベーションには近づく方法、と思って研究を進めています。
――みなさん色々な方と連携して、様々な取組みをされていますね。そのような産学官民連携での研究活動の中で、おもしろい、と思った瞬間は何かありますか。
金森 それぞれの業界にある慣習がおもしろいです。たとえば、システム検証を、商社の人は1か月やって次の一手を判断することもありますが、土木の人間からするとある程度普及するかまで見たくなるので数ヶ月は実施したい、また行政からすると年内で一回の実験を複数年、たとえば3年ぐらいが普通となる。ぜんぜん感覚が違う。
慣習が違うので調整はむずかしいところでもあり、おもしろいところでもある。社会実装を本当にやるんだったら、そういう調整をする人も必要と思います。それが大学の役割かどうかはわかんないですけど、僕は自分でデータを使えるようにしたいので、その権利をいただけるように立ち上げから関わろうと思っています。
赤井 最近は企業にも、様々な分野で博士号を取った人がいます。彼らはもともと深い知識を持っていて、その上で真剣に開発に取り組んでいます。なので、深い知識と経験を有する彼らとの議論は、かなり深くて鋭いです。そんな彼らと議論できるだけでも、大学内では感じることができない感覚を味わえます。
企業は安全を追求した開発を全力で行っているからこそ、既存システムの限界をものすごくよく理解しています。一方で大学は、マンパワーの問題もあり、開発に全力を割くのはむずかしいのが現状です。では、我々大学は何を研究すべきかということを改めて考えて、今できないことをできるようにするための新たな技術を提案しなければならない、と強く考えるようになりました。それがまさしく、既存システムの限界の突破を実現する、ということです。
大学も企業も、「良い技術・モノ」を作るというベクトルは同じですが、取り組んでいることが違います。一般的なことですが、企業は開発、大学は研究をがんばっています。そういう意味では、お互いがお互いを求める部分は多くあります。しかしながら、しっかりと連携をするためには、自分だけでなく相手にも本気になってもらわないといけません。つまり、大学の研究が魅力的であるということを発信していかなければいけない、とあらためて感じられたところは、おもしろい経験になったと考えています。
小野島 異分野の人材交流ができることが魅力のひとつです。我々が学会発表や展示会などの外で会うのは基本的に同質な人の集まりで、いいね、と言うポイントも、持っている課題意識も一緒で、その解決法が見つかることは実は少ない。会社って異質な人の集まりとして部署が形成されていたり取り組む人が構成されています。多様な意見をもらえますし、こちらも多様な視点で自分の研究を見つめ直すことができます。
2つ目は企業の中身を知ることができる。大企業、中小企業、スタートアップが、どんなふうにできあがって、どんな構成員で、どんなふうに動いているのかを知ることって外側からはなかなかむずかしい。ですけど、一緒にやるといろんなことが見えてきます。企業活動の仕組みを知ることは、地域とその産業構造を知ることにつながってとても興味深い。知ることで社会実装のためのアプローチに対する視点を持つことができます。企業の動き方とか成り立ちとか、目指しいているもの、必要なもの、足りないものがわかると、お互いのいいところを高め合ったり、足りないところを補いあったりする関係性にマッチングする確率が高まります。それぞれの良さを認識しあうきっかけになりやすいので、一緒にやることはいいことだと思いますし、とってもおもしろいことです。
医療工学の小野島さん、土木工学交通系の金森さん、そして、情報学の赤井さん。それぞれの視点で自身の取組みについて語っていただきました。
さて、次回はそれぞれがお互いに聞きたいこととして用意した質問に答えてもらいます。
次回の更新をぜひともお待ちください。⇒part.2を公開しました。
赤井さんが参加するグループ 知能化モビリティグループ
小野島さんが参加するグループ バイオデバイス加工グループ
金森さんが参加するグループ 交通・情報システムグループ、ゆっくり自動運転グループ
〔NU COIマガジン バックナンバー〕
第4回「名古屋大学COI若手顕彰受賞者インタビュー」part.1 part.2 part.3
※所属・役職などは公開当時のものです。
公開:2020年 1月14日