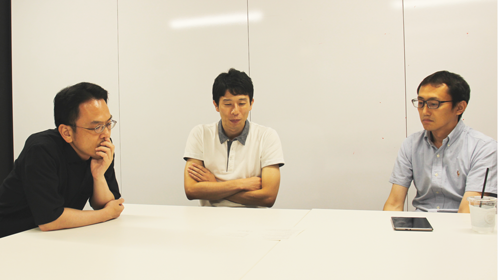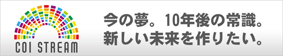NU COIマガジン第4回「名古屋大学COI若手顕彰受賞者インタビュー(2)」
2020/01/20
さて、前回に引き続き、今回も名古屋大学若手顕彰を受賞した3名へのインタビューをお送りします。
医療工学の小野島さん、土木工学交通系の金森さん、そして、情報学の赤井さん。異なる分野の研究者であるお三方が、お互いに聞いてみたかった質問とは。
――次は赤井さんからの質問です。ひとつは、起業するためにすべき研究とはどのようなものか、もうひとつは、いわゆる「役に立たない研究」をどう思うか。
金森さんはベンチャー経営に関与されていますし、小野島さんはベンチャー創出の公募プログラムを獲得されています。赤井さんからベンチャー経験者への質問、ということですね。
金森 役に立つ・立たないって、研究論文と一緒で向こう側が判断するので、我々からはなかなか判断しづらいですね。あとは、これとこれをかけ合わせたらいける、という、そこの発想や知識は圧倒的に持ってた方がベンチャーをやる時にいいかな。自己解決型でやるとすぐに限界があって当たり外れも激しいので。この技術で誰と組んだらこういうことできる。その連携のしやすさみたいなものを赤井さんが持つと、かなり幅が広がって、組合せが増えると向こう側からも当たる可能性が高くなるんじゃないかな、と思います。

赤井 こっちが持っている技術だけでなくて、それを応用するためのネットワークというか。
金森 そうそう。ベンチャー業界ってネットワーキングの方が重要だって聞くし、利用者目線で異分野連携をやるようになってきているかなと。
小野島 起業するためにすべき点は実用化に結びつきやすい要素に研究を分解することだと思います。他の人と一緒にやって初めて価値が生まれそうな、もしくはつながる要素を明確にした研究は起業につながりやすい。実用化するってことは社会にニーズがあったり、課題解決の要素を含むってことで、その取組み方は多角的な技術であるはず。スマートフォンひとつとっても、デバイス技術だけじゃなくて、通信網の整備技術の開発も含まれる。
ひとりでやるよりも成果も可能性も広がるから、連携や共同研究をした方がいいと思う研究者は多い。URAやVCのようにつないでくれる人はいるけど、どんな人とつながりたいかを発信できるのは自分だけ。ひとりで完結しないで、足りないところを積極的に開示して助けを求めていくことです。
金森 仮説の置き方や自由度を上げておくと、同じ技術でも解釈論と同じように変わっていくかもしれない。ネットワーキングでいろんなことができるんじゃないかな。今、自動運転の人たちが、ワーッと赤井さんに寄ってきてると思うけど、たぶんその分野だけじゃないと思うから。

小野島 新しい技術を入れた方がいいって思う人と、慎重にって思う人との比率が逆転するタイミングって絶対ありますよね。そこをうまくみながら、その境目ぐらいでアプローチをかけていくと、一緒にやる仲間を見つけやすいかもしれません。社会的なニーズ、もしくは変化の中から拾うと、ほんとに今までやってきた研究とそんなに変わらなくても、設定の仕方で起業しやすい研究に変わっていくような気がします。
赤井 これは情報系が特にだと思うんですけど。今、研究者が企業に流れていることが多いんです。大学が研究機関として負けないためには、それに見合う、それを越えるような「役に立つ研究」をしてかなきゃ振り向いてもらえない。そうはいっても、知識人たちの娯楽みたいなものが研究のはじまりになってるわけじゃないですか。だから、知識欲を満たすための研究ってのは大学として然るべきだと思うんですよね。ただ、そんな研究しててベンチャーできるとはとても思えない。
今起業してみた上で、プラス大学人であるお二方にとって、いわゆる「役に立たない研究」って、どうゆうふうに見えるのかな、て言うのが気になります。
小野島 大学には、知識のアーカイブをどんどん更新して、アップデートされたものに人々をつないでいく、というミッションが社会的にあると思います。同じソフトウェアの開発をするのであっても、大学でやることの意義と、企業でやることの意義で、それぞれに異なる価値があると思うので、それがおもしろいと思える場所を選んで研究できればいいんじゃないかな。
金森 大学は真理を求める自由度があるんですよね。商品化で社会貢献する目標がある民間企業だと、どうしても評価されない気もする。小野島さんが言ったように、失敗したことも含めて蓄積していくのは大学として重要なのかな。他人から役に立たないと思われながらも、その人が真理に向けて必要だと言っていれば、それはおもしろいアプローチだよね、て言う組織が大学だと思う。
あと、情報系ではデータ量に依存した研究とか技術革新が進んでいて、そこは大学が弱いところですよね。中国の企業が一番技術力を持っているというのは、もうどうしようもない流れで、そこはまた違うアプローチで進めることも実は大学だとできるし。AIの研究者は最終的には知能のあり方を知りたい哲学系の方も多いですよね。
赤井 多いですね。
金森 心理とか、既存手法でデータがなかなか観測できないところもあるので、そういったところは奇抜なアプローチでやってく。今あるデータだけから効率的な技術更新するのに興味があるなら民間企業に行った方がやりたいことができるのではないかな。
小野島 開発をとにかく進めたい、性能がすごいものをつくりたいときの優位性は企業にあって。一方で、そのために作られたツールを使ってサイエンスする、というアプローチが大学の得意なところ。それは「役に立つ・立たない」以前の問題で、金森さんの言葉を借りると、真理の探究、なんですよね。不変なもの、実はまだ分かってないけど未開な人間の中にある仕組みはなんだろう、とか。今までわかってなかったことにチャレンジできる。
誰もやっていないことをやったり、世界で初めてのことをやるのは、やっぱり大学の役割。サイエンスとして、ゼロだったところをイチにするわけですから。世界で初めての発見があると、それをベースに社会との接点を探して、起業の種を見つけられれば、それは大学からベンチャーを作ることに直結します。そうでないと、大学発ベンチャーでやる意味がないですよ。既存のアイデアを組み合わせて新しいアプリケーションを作るだけでなく、サイエンスの研究活動をともなっていることが、大学発ベンチャーにとって重要だと思っています。
受賞者同士の質問はまだまだ続きます。
これから先の未来における社会の変化や、三者三様の野望が語られました。
次回の更新をぜひともお待ちください。
赤井さんが参加するグループ 知能化モビリティグループ
小野島さんが参加するグループ バイオデバイス加工グループ
金森さんが参加するグループ 交通・情報システムグループ、ゆっくり自動運転グループ
〔NU COIマガジン バックナンバー〕
第4回「名古屋大学COI若手顕彰受賞者インタビュー」part.1 part.2 part.3
※所属・役職などは公開当時のものです。
公開:2020年 1月20日