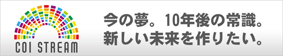NU COIマガジン第4回「名古屋大学COI若手顕彰受賞者インタビュー(3)」
2020/01/27
最終回となる今回は、未来の話に野望の話と盛りだくさんです。
COIプロジェクトは、「10年後の日本が目指すべき姿」からバックキャストした研究開発として、2013年にスタートしました。2019年度の今は、その7年目、あと2年でプロジェクトは終了します。
しかし、研究開発がすべて終了するわけではなく、COIプロジェクト終了後も、継続するテーマ、あるいは新しいテーマでの研究開発は続きます。
彼らが描く未来とは、抱く野望とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
――次は未来を見る質問です。小野島先生からは、2020東京五輪と2025大阪万博後の、社会が目標とする技術革新のタイミングとは、金森先生からは、リニア新幹線が開通する影響、東京まで一時間の世界観とは、です。
小野島 東京五輪とか大阪万博って、みんなが理解できる言葉としてすごく説得力がある。仮でも目標が設定されるとやろうとドライブがかかる。だから、2025年よりも先の世界にマイルストーンを持った方がいい気がします。情報の世界、都市計画、モビリティの世界、私みたいな医学やバイオの世界で。次のタイミングをお互いに共有しておくと未来を考える上で楽しいかなと。
金森 この50年ぐらい通勤時間が変わっていないってデータで観測されてるんです。だいたい1時間弱ぐらい。昔は東京圏で閉じていたのが、新幹線が延伸すると長野から宇都宮から来たり。そう考えると名古屋から通うも当然出てくる
小野島 人の流れ方が変わっちゃいますね。
赤井 技術革新のタイミングの予測は難しいですよね。最近はロボットを使っていろいろやりたいという話はよく聞きますが、そのやりたい内容が5年前と変わっているかと言われると、あまり変わっていないような気もします。
だけど、5年前と比べればその規模感が変わった、という実感はします。その意味では、近々ロボットを活用した技術革新が起こると思いますが、実際に何年後にロボットが社会に入ってくるのか、なかなか想像ができないですね。
小野島 個人的にはインターネットの通信が5Gとかもっと先までくると、移動しなくてもすむことがきっと増えてくる。移動速度を速める以外の方法で移動のイノベーションが起きてくる気がします。
金森 国交省で歩くためのまちづくり、あえて人と会う大切さを大事にする出会いの場を街の中に埋め込もうという検討もあります。なんでシリコンバレー的な場所ができるかって、しっかり解明できてないんです。なんかニーズがマッチしたあの場所にいたから、生の情報が得られるからみんな集まっちゃってる。我々も今日、こうやって三人で話してる。何がどういう話題になるかわかんないけど、有益な情報ってかなりあるはず。それは電話とかインターネットとかで話しているだけだと、たぶん生まれない。
小野島 コミュニケーションのハードルが下がるっていう意味では、未来はたぶんその方向で変わると思う。移動はしなきゃいけない所では絶対しなきゃいけないし、直接会うからこそできあがるコミュニティももちろん継続していくだろうから。
金森 そうなると、ひとつの拠点でなくて、多角的な拠点になるんだろうな。大学も企業も3つか4つぐらい所属できたり、毎日違うところで違う仲間と仕事する、みたいな。
――東京五輪や大阪万博の先の未来では、移動にまつわる変化が様々なところに波及するのかもしれないですね。

小野島 高度経済成長の後、老朽化したものを置き換える課題と、高速移動や通信技術を盛り込んで新たに整備する設備・まちづくりを考えると、そろそろ更新のタイミングに来ていると聞きます。コネクテッドなIOTベースのまちづくりとなった時に、従来のインフラや都市計画の配置ではまかなえないものとか、置きかえなきゃいけないものとかがある。だから、あと20年ぐらいで、私はまちががらっと変わってくれることを期待しています。
金森 日本って道が狭いんです。それは歩く文化だから、江戸時代はそれに最適化されたらしいです。ヨーロッパとかは馬車で動くのが一般的だったから道が広い。都市をそのときの文化で最適化やカスタマイズする。だから移動手段とまちづくりの更新時期っていうのは、確かに今聞いて、ああなるほどなあ、と。
小野島 皆さんの予想が正しければ2040年ぐらいに移動を中心とする、もしくはコネクテッドなまちづくりとしてのインフラの大刷新があると期待して、今後の研究の展開を想像したいですね。
――さて、最後の質問は小野島先生からのものです。ずばり、ポストCOIの個人的な野望について。COIプログラムはあと2年半ほどで終了しますが、その後、個人的に抱いている野望について教えてください。
小野島 私は未来社会創造機構を、社会実装研究のための研究者が集まる部局として独立させてもらいたいなと思ってますね。
COIは、バックキャスティングで研究計画をして取り組んできた壮大な実験で、できたこととできなかったことがあると思う。私が思うできたことは、大学が持つ設備や人材などの中にフィットする部分を見つけられたこと。できなかったことは、フォアキャスティングな研究計画の場合と同じくらいの時間をかけることになったこと。
COIを経験した人たちは、きっともっと効率的な方法を考えられるはずだし、従来の先生たちとは違うノウハウとか知識を持っているはず。そういう人たちが自分の研究もしながら、実用化の案件を受託したりできたらうまく回るんじゃないかな。
金森 ずっと大学にいれるとは思ってなくて、でも大学にはいたいなと思っているスタンスです。まあ、3つぐらい掛け持ちできるような、そういう大学の働き方のシステムがあればうれしいかな。
僕ら土木的なところだと、時々いきなり市長や社長に会ったりすることもあるけど、それは大学に信頼があるよさだと思う。でも、大学にずっといたらできないこともあると思います。そこはいろいろ使い分けられるよう、3つぐらいの名刺を持ちたいと思ってます。みんな研究成果を社会実装するために起業すればいい。起業も1個2個じゃなくって、いろんな人たちと組んで。で、失敗した人たちがまた大学に戻る。そういうのでもいいのかな。
赤井 趣味のバレーボールサークルで大学以外の一般のの人たちとも会うんですが、この世界が生きづらいと感じている人が多いなと感じます。それを少しでも変えられるようなことができればいいなと考えています。まずは、今の研究トピックである自動運転で活躍して名を上げて、自分が「あったらいいな」って思える社会を目指せるぐらいの発言力を手に入れたいですね。
小野島 学問を修めている人は、社会の中で一定の尊敬と信頼を集めるものですよね。影響力を持って社会をいい方向に変えることに強く希望を持つのであれば、私はアカデミアというのはいい世界だと思います。企業の立場では会えない人や話せない内容がいろいろあると聞きます。でも、大学の立場だと自由に話をしたり聞いたりできる機会が多いと感じます。私たちは、社会の中でそういう中立的な立場にいることを誇りに思って声を届けられれば、説得力も増してくるような気がします。
金森 あまり給料をもらってないっていうのもみんな知ってるから。奉公してるみたい。(笑いが起こる)
――それではお時間となりましたので、これで終えたいと思います。本日はいろいろお話しいただき、ありがとうございました。
終始わきあいあいとした、しばしば笑いが起こるインタビューでした。
大学とは何か、大学人とはどんな存在か。最後はみなさんの野望に加え、自分たちが期待する大学の姿が語られたように思います。
研究者は、しばしば自身の研究に閉じこもるようなイメージを持たれているのではないでしょうか。しかし、実際はそんなことはなく、インタビューで語られたように、自身の研究分野だけでなく、その外側、社会に対して、広い視野を持っているようです。
NU COIマガジンでは、目の前の研究開発だけでなく、その先の社会も見つめて取り組む姿を、今後も取り上げたいと思います。
赤井さんが参加するグループ 知能化モビリティグループ
小野島さんが参加するグループ バイオデバイス加工グループ
金森さんが参加するグループ 交通・情報システムグループ、ゆっくり自動運転グループ
〔NU COIマガジン バックナンバー〕
第4回「名古屋大学COI若手顕彰受賞者インタビュー」part.1 part.2 part.3
※所属・役職などは公開当時のものです。
公開:2020年 1月27日