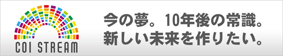NU COIマガジン第5回「歩行トレーニングロボットが導く未来」
2020/03/31

〔目次〕
日曜日、Dさんはウォーキングイベントに参加した。足首のねん挫をきっかけに、出かけることがおっくうになったのを見かねて、孫娘が誘ってくれたのだ。孫娘に手を引かれ、足や腕の動きを意識ながらコースを歩き、無事にゴールできたときはとてもうれしく、自信がついた。ゴール記念のスタンプを見るたびに、その時の気持ちがよみがえる。スタンプをためることも楽しくて、それからたびたびウォーキングイベントに参加するようになった。
あの時、孫娘が自分を誘い出してくれたことを、Dさんはとても感謝しているそうだ。

歩くことをむずかしいと思っている人ほど、外出の頻度が低くなる。そんな可能性があることを内閣府の調査が示している※1。調査によれば、「掃除や散歩など適度な活動」や「数百メートルくらい歩くこと」をむずかしいと感じている人は、外出の頻度として「週に2~3日」を選ぶ人が最も多かった。
名古屋大学COIでは、すべての人が活躍できる社会の実現のため、移動を支援する製品やサービスの研究開発に取組んでいるが、そもそもの「歩く」ことへのアプローチも重要だと考えている。
人の移動は徒歩からはじまった。そこから、馬などの利用、馬車の登場、そして自動車の登場と、移動のための手段は多様となった。しかしやはり、自らの足で思うままに歩いていける楽しさと、それがもたらす自信は、いつの時代人々の支えとなったのではないだろうか。もしその自信を失えば、外出への意欲も低下してしまうかもしれない。
では、どうしたら人は「歩く」ことに自信を持てるのだろうか。
「実際に自分がどれだけ歩けるかがわかれば自信につながるのではないか、と私たちは考えています」と話すのは、歩くこと、に注目した研究開発をする山田 和範特任准教授だ。
「最終的には自宅での利用を考えていますが、まずは介護施設向けのトレーニングツールとして開発を進めています」
山田さんが押して歩いてきたのは、ハンドルのオレンジと白い本体が印象的なロボットだった。形として似ているのは四輪の歩行器だが、ロボット、と言うだけあって、いろいろと仕掛けがあるそうだ。
「ここを見てください」と示されたのは、ハンドルの下にあるモニタ。ハンドルを押して進むときにちょうど見やすい位置にある。
「このモニタには、その人の今の歩行状態が表示されます」
山田さんが歩くと、モニタには速度や歩行時の左右バランスなどが表示される。
リアルタイムな歩行能力の分析を可能としたのは、名古屋大学で培われてきた荷重センシング技術だ。様々な歩行能力が、ロボットに搭載された荷重センサによるセンシング結果をもとに分析可能となる。
しかも、ただ分析するだけではない。モニタを操作すると、運動負荷を設定する画面に切り替る。押すときの重さなどを調整できる。歩行状態に合わせた適度な負荷をかけることで、トレーニングにもなるようにデザインされている。
まるでフィットネスマシーンのようなもの。それが歩行トレーニングロボットなのだという。
「トレーニングをする人が使って楽しく、自慢ができること。施設スタッフの負担も軽減できること。これらが両立できるよう、見た目や機能をデザインしました」と説明してくれたのは、横矢 真悠特任講師だ。
今のモデルは3度の改良を経たものだという。これまでの変遷を見ると、円筒形に近い本体が4輪歩行車に近い形状になるなど、形や機能がだいぶ変わっている。
そのような改良を可能にしたのは、病院と介護施設の協力だった。
2016年の夏、山田さんと横矢さんは、病院や施設にプロトタイプを持ち込んだ。高齢者を中心とした利用者側の意見を集めるほか、医師や理学療法士、介護スタッフなどとの意見交換もするためだったという。
「はじめは不安でしたが、思ったよりみなさんに楽しそうに使っていただけました。いろいろと率直なご意見もいただき、手応えを感じました」
見た目や足回りのほか、「使い続けたい」と思われるための機能についての意見もあったという。そのひとつとして、「効果が見えないと利用者のやる気が続かない」というものがあった。
ちょうどその時、平成30年度介護報酬改定がなされ、その目玉のひとつが「自立支援」だったことも後押しとなった。高齢者自身が自立した日常生活を維持できるよう制度が変わったのだ。
加えて、訓練効果の見える化は、現場のスタッフにとっても記録やプラン作成の面でメリットがある。
「どういったものがいいか、いろいろ伺いました。もともと個人認証の機能は持たせていたので、それと組み合わせる形で、利用者ごとにこれまでの記録を出力する機能を持たせました。また、介護報酬請求に必要な記録を自動で作成する機能も搭載しました」
利用者にとっては、これまでの自身の変化を確認できることが訓練への励みとなる。施設側にとっては、利用者の変化を細かく数値で把握できるとともに、わざわざ計測したり入力したりする手間が省けることで、作業負担の低減が図れるというわけだ。
「今、どんなものがほしいのか。エンジニアである私たちには見えていないことが多くあります。だからこそ、実際に使う人、実際に使われる場所での検証が大事だと思っています」

継続的に現場の声を収集し、よりよくなるよう試行錯誤する。そして、改善策を反映したプロトタイプを現場に持ち込み、使ってもらう。
そのプロセスを繰り返したことは、着実に製品の良さにつながっている。最新のモデルは、2018年度グッドデザイン賞 ベスト100※2やIAUD国際デザイン賞2018 金賞※3を受賞しており、展示会などに出展するたびに様々な引き合いがあるという。対外的にもその良さが認められつつある。
2019年度はこれまでとはタイプが違う施設にもロボットを持ち込み、現場の人とともに、新たなアイデアの種を探しているそうだ。
ところで、いつまでも元気に自分の足で外出するためには、歩行能力をはじめとする身体機能に加えて、物事を理解したり判断したり、記憶したりする認知機能も重要だ。どちらか片方だけでも弱くなればひとりでの外出が少し難しくなる。
この2つを同時に鍛えることはできないのだろうか。
間瀬 健二教授の研究室では、まさにそれを実現させるべく、トレーニングプログラムの研究開発に取り組んでいる。
「目指すのは、転びにくいように身体機能と認知機能を同時に鍛えるシステムです。そのために、手軽で、実生活において効果のあるトレーニング方法を研究しています」
それは簡単に言えば、体を使いながら、頭も使うプログラムだ。歩行トレーニングロボットを使って指定のコースを歩きながら、ロボットのモニタに表示されるマークの種類に応じたボタンを押す。つまり、歩行トレーニング課題と認知トレーニング課題という、複数の課題を同時にこなすことになる。
このトレーニングプログラムの効果検証は、高齢者を対象とした次のような実験で行われた。
実験参加者は、2種類の課題を同時に行うグループと、別々に行うグループとに分けられ、週2回のトレーニングを約1か月間受けた。その結果、2種類の課題を同時に行ったグループの方が、別々に行ったグループよりも、身体能力や認知能力が良くなる傾向がみられたという。※4、5
研究室では更なる改良のほか、使い続けてもらえる工夫もしていると、間瀬さんは説明してくれた。
「やり続けると良いことがある、とわかっていても続かないことはよくあります。それは多くの人が身を持ってご存知ではないでしょうか。そのため、プログラムのゲーム性を高めるなどして、トレーニングを楽しんでいる内に健康にもなっている、という状態を目指しています」
2019年7月に、令和元年版高齢社会白書が公表された※6。白書によれば、日本の高齢化率は28.1%であり、65歳以上の方がいる世帯は全世帯の約半分にあたる。また、三世代同居は年々少なくなり、夫婦のみや一人暮らしの世帯が増えている。世界と比べて日本の高齢化率は最も高く、今後もそれを維持していくと考えられている。
このような日本が抱える社会状況から、今後多くの社会問題が想定される、と研究を統括する新井 史人教授は言う。
「すべての人が活躍できる社会の実現のため、私たちは“歩く”ことに着目しました。何らかの理由で、その“歩く”ことが困難になった方々がいます。そのような方々の歩行トレーニングや歩行そのものを支援することが重要だと考えました」
ロボットの基本構想は2013年にまとめられ、それから多くの人々の尽力と協力によって、ようやく介護施設などの現場での実証実験ができるまでになった。その際に大切にしてきたのは、ロボットを利用する人はもちろんのこと、トレーニングを見守る人、施設を運用する人々など、直接間接を問わず、様々な立場でロボットを使う人々にとってよいものとすることであったそうだ。
「どんなことが必要なのか、何が大事なのか。そうやって様々な機能を開発し、効果を検証してきました。このようなロボットが実用されることで、健康寿命の延伸や、QoL(生活の質)の向上につながることを期待し、今後も研究開発を続けてまいりたいと思います」
研究者が現場の声に導かれて研究開発する歩行トレーニングロボット。そう遠くない将来、そのロボットが、多くの人々を生き生きとした生活へと導いていくだろう。
そう願いを込めて、今日も研究者たちは現場へと足を運び続ける。
〔参考文献〕
- 内閣府(2015)平成26年度 高齢者の日常生活に関する意識調査結果.
- 2018年度グッドデザイン賞 ベスト100
- IAUD国際デザイン賞2018 金賞
- 岡田直人、渥美裕貴、横矢真悠、山田和範、汪雪テイ、上出寛子、森田純哉、榎堀優、間瀬健二. (2018). 心身マルチタスク訓練による身体能力改善効果の検討. 研究報告エンタテインメントコンピューティング (EC), 2018-EC-48, 1-6.
- 渥美裕貴、横矢真悠、山田和範、森田純哉、平山高嗣、榎堀優、間瀬健二. (2017). 心身マルチタスク状況下における認知タスク負荷評価の検討. 人工知能学会全国大会論文集 第 31 回全国大会(愛知県)
- 内閣府(2019)令和元年版高齢社会白書
〔NU COIマガジン バックナンバー〕
第4回「名古屋大学COI若手顕彰受賞者インタビュー」part.1 part.2 part.3
※所属・役職などは公開当時のものです。
公開:2020年 3月31日