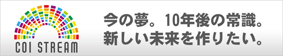「CASE研究会拡大版シンポジウム(2/10)」を開催しました
2020/06/09
※2020/06/09轟木氏の資料を追加しました。
2月10日(月)、名古屋大学 ナショナルイノベーションコンプレックスにて、「CASE研究会拡大版 自動運転の社会実装に伴う法律問題を考えるシンポジウム」を開催しました。
昨年の1月より毎月1回、毎回2名の講師をお招きして開催してきたCASE研究会ですが、今回は拡大版として、6名の講師をお招きし、中京大学 法務研究所との共催のシンポジウムを開催しました。
本シンポジウムでは、6名の講師から、官公庁の取り組み、実装を見据えた法的課題、事故時の法的責任、の大きく3つのテーマでそれぞれ講演いただきました。
まず、官公庁の取り組みとして、国土交通省と警察庁からそれぞれ講師をお招きしました。
国土交通省の池田 圭佑氏(自動車局 技術政策課 専門官)からは、「自動運転の実現に向けた国土交通省の取組」と題し、講演いただきました。国際基準の検討状況や道路運送車両法の改正内容について詳しく説明いただくとともに、保安基準などの策定状況などに関する最新情報をご紹介いただきました。〔講演資料(クリック)〕
続いて、警察庁の森田 正敏氏(交通局 交通規制課 交通管制技術室 室長)からは、「自動運転の実現に向けた警察の取組について」と題し、講演いただきました。自動運転の実現に向けた警察の取組みとして、自動運転車への信号情報の提供や交通流に関するシミュレーションなどの実証実験などについて紹介いただきました。〔講演資料(クリック)〕
 |
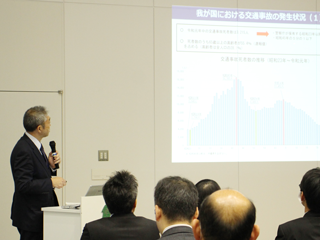 |
| 池田氏の講演の様子 | 森田氏の講演の様子 |
次に、実装を見据えた法的課題として、実証実験や模擬裁判に関わる法律実務家の方々からそれぞれ講演いただきました。
まず、自動運転OS(基本ソフト)「Autoware(オートウェア)」を開発する自動運転のスタートアップである株式会社ティアフォーにて、法務部長を務める轟木 博信弁護士(株式会社ティアフォー 管理本部 法務部長)より、「自動運転の社会実装に伴う法的諸問題」と題し、講演いただきました。
金融分野で起こった縦割りの規制から機能的・横断的規制への変化をご紹介いただいた上で、自動運転に関する法規制に必要な変化について、あるいは自動運転事業のパターンごとの法的な懸念などについてお話しいただきました。〔講演資料(クリック)〕
また、明治大学自動運転社会総合研究所の客員研究員であり、同研究所が実施してきた自動運転に関する模擬裁判にも関わっている吉田 直可弁護士(法律事務所愛宕山)からは、「自動運転車の作動状態記録装置の課題と紛争解決」と題し、講演いただきました。
レベル4自動運転が社会インフラとなるために、運行設計領域(ODD: Operational Design Domain)設定の際には技術的側面のほか、利用者や地域住民のリテラシー、および地域ごとの保安基準が必要になるだろうとの見解をお話しいただきました。また、2019年5月の道路交通法改正により自動運転車に設置が義務付けられた作動状態記録装置について、客観的データの存在で事故処理が精密に行えるようになるとの期待があること、そのための装置の仕様に関する提言などについてもお話しいただきました。〔講演資料(クリック)〕
 |
 |
| 轟木氏の講演の様子 | 吉田氏の講演の様子 |
事故時の法的責任については、民事責任と刑事責任について、それぞれ講演いただきました。
民事責任については、栗田 昌裕教授(名古屋大学 大学院法学研究科)から、「自動運転車の事故に関する民事責任とその帰責原理」と題し、講演いただきました。
まず、近代法にて採用された過失責任主義の現代における修正について説明いただいた後、自動運転のSAEレベルごとに一般不法行為責任、運行供用者責任、そして製造物責任のそれぞれがどのように扱われうるかについて、説明いただきました。また、今後の自動運転車による事故における民事責任のあり方についてもお話しいただきました。〔講演資料(クリック)〕
刑事責任については、本研究会の幹事でもある中川 由賀弁護士(名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授、中京大学 法学部 教授)が「自動運転移動サービスにおける自動運行装置作動中及び遠隔操作中の事故の刑事責任」と題し、講演しました。
まず、国内外における法整備の現状について紹介した後、事故事例を挙げ、従来型手動運転自動車の場合と比較する形で、遠隔監視システムによる無人自動運転車の場合の刑事責任について説明し、責任主体として、遠隔監視操作者、整備管理者、管理者・監督者、及び自動運転車作成者のそれぞれの想定される過失責任についてお話ししました。〔講演資料(クリック)〕
 |
 |
| 栗田氏の講演の様子 | 中川氏の講演の様子 |
昨年の1月から、毎月1回、理解と文系から一人ずつ講師を招き開催してきたCASE研究会ですが、定期的な開催は今回が最後となります。
来年度は、我々、名古屋大学COI法制度整備ユニットの面々が各地に出向き、自動運転に関わる方々と意見交換をさせていただくことを通じて、知見を深めてまいります。そして、その成果などを踏まえ、秋と春の2回、シンポジウムを開催する予定です。
〔これまでの開催〕
関連:
公開:2020年2月25日
更新:2020年6月9日 資料の追加